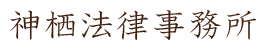2018年04月11日
 示談にあたって,事故当事者の判断能力が低下している場合に,誰を相手に示談をすべきかという問題があります。
示談にあたって,事故当事者の判断能力が低下している場合に,誰を相手に示談をすべきかという問題があります。
1 大阪高判平成27年9月30日
交通事故で死亡した被害者の相続人A(中度の知的障害がある)が,A名義で保険会社と示談書を交わした事案です。A名義の口座に保険金が入金された後,Aとは別人により払戻しがなされ,その後に後見開始審判がなされました。
裁判所は,本人の発達年齢が6歳程度であったこと,示談内容の複雑性などから,各示談を無効とし,A名義の口座に入金された弁済の効力も否定しました。
2 大阪高判平成22年9月15日
交通事故により急性硬膜下血腫等を受傷した被害者A(79歳女性・後遺障害別表第一2級1号)の長男Bが代理人として示談書を取り交わし,B名義の口座に入金しましたが,Bが保険金をAに渡さず,訴訟となりました。
一審裁判所は,示談交渉を委任したと認める事情がないなどとして示談の効力を否定しました。
しかしながら,上記高裁判決は,Aなりの合理的な意思決定に基づく委任があったとして,示談を有効としました。
3 検討
判断能力の複雑性からすると,判例1(示談内容の理解)を無効としつつ,判例2(委任の理解)を有効とすることも考えられますが,判例1は,本人Aに払っているにもかかわらず,弁済の効力が認められないこととなり,支払側からすると酷な結論になっています。
支払にあたっては,相手の判断能力をきちんと確認し,場合によっては,成年後見制度等の活用をすることが有用です。